発達障害の診断を受けるべきか|エンジニアとしてのメリット・デメリット

「もしかして自分は発達障害?」「診断を受けた方がいいのか」「でも診断されたら人生終わり?」
ネットの診断テストで高得点が出て、不安になっているあなた。診断を受けることは、決して人生の終わりではありません。むしろ、より良い人生への第一歩になる可能性があります。
この記事では、エンジニアという職業の観点から、診断を受けることの意味とその後の選択肢について、実体験を基にお伝えします。発達障害の転職全般については発達障害の転職で失敗しない7つのポイントも参考にしてください。
【理解】発達障害の診断とは何か
診断の意味と目的
診断とは何か
- 定義:医学的な基準に基づく判定
- 目的:
- 困りごとの原因を明確にする
- 適切な支援を受けるため
- 自己理解を深めるため
診断は違います
- レッテル貼りではない
- 能力の否定ではない
- 可能性の制限ではない
主な診断基準
ADHD(注意欠如・多動症)の診断基準:
- 不注意:9項目中6項目以上
- 多動性・衝動性:9項目中6項目以上
- 継続期間:6ヶ月以上
- 発症時期:12歳以前
ASD(自閉スペクトラム症)の診断基準:
- 社会的コミュニケーション:複数の状況で困難
- 限定的な興味:2つ以上の特徴
- 幼少期から症状の存在
- 日常生活への臨床的に意味のある影響
グレーゾーンについて
- 定義:診断基準を完全には満たさない
- 現実:困りごとはある
- 対応:支援を受けられる場合もある
エンジニアに多い傾向
プログラミングとの親和性
- 規則性:明確なルールがある
- 論理性:感情より論理を重視
- 集中:没頭できる環境
職場環境の特徴
- リモート:対人ストレス軽減(詳しくは発達障害者にとってフルリモートは天国だった件参照)
- フレックス:自分のペースで働ける
- 成果主義:過程より結果重視
よくある悩み
技術面:
- 過集中で他が見えない
- ドキュメント作成が苦手
- 締切管理ができない
対人面:
- チーム作業が苦手
- 会議で発言できない
- 雑談ができない
キャリア面:
- 昇進したくない(管理職回避)
- 転職を繰り返す
- 評価されない
【分析】診断を受けるメリット
1. 自己理解と受容
診断前の自己認識
- 「なぜ自分だけできない」
- 「努力不足だ」
- 「性格が悪い」
- 「甘えている」
診断後の変化
- 「脳の特性だった」
- 「工夫次第で改善可能」
- 「自分を責めなくていい」
- 「強みもある」
具体的な変化
仕事面:
- 苦手なタスクの理由が分かる
- 対策を立てやすくなる
- 無理な頑張りをやめられる
人間関係:
- コミュニケーションの課題が明確に
- 相手に説明しやすくなる
- 理解者が増える
メンタル面:
- 自己肯定感の回復
- 二次障害の予防
- 適切な目標設定
2. 支援とサポートへのアクセス
医療的支援
薬物療法(ADHD):
- コンサータ:集中力改善
- ストラテラ:衝動性抑制
- インチュニブ:多動性改善
効果:
- 仕事の効率UP
- ミスの減少
- 感情の安定
カウンセリング:
- 認知行動療法:思考パターンの改善
- SST(社会技能訓練):対人スキル向上
- 心理教育:特性の理解
社会的支援
障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳):
- 税金の控除
- 公共料金の割引
- 就労支援
就労支援:
- ハローワーク:専門援助部門
- 移行支援事業所:スキル訓練
- ジョブコーチ:職場定着支援
会社での配慮
合理的配慮の例:
- 静かな席の確保
- 指示の文書化
- 締切の見える化
- 定期面談の実施
※診断書があると交渉しやすい。詳しくは職場での合理的配慮の求め方完全ガイドを参考にしてください。
3. 適職探しとキャリア形成
自分に合った職種選び
向いている職種:
- 専門性の高い技術職
- 研究開発
- クリエイティブ職
避けた方がいい職種:
- マルチタスク必須
- 対人折衝メイン
- ルーティンワーク
環境選び
ADHD向けの環境:
- 変化のある環境
- 裁量権がある
- 成果主義
ASD向けの環境:
- 構造化された環境
- 明確なルール
- 専門性を活かせる
転職活動での選択肢
オープン就労:
- メリット:配慮を前提に選考
- 企業:ダイバーシティ推進企業
- 選考方法:
- 一般枠:通常の選考
- 障害者枠:配慮ありの選考
【懸念】診断を受けるデメリットと対処法
ストレス管理については発達障害エンジニアの職場ストレス管理術も参考にしてください。
心理的な影響
よくある不安と現実
「障害者というレッテル」
- 不安:偏見を持たれる
- 現実:
- 言わなければ分からない
- 理解者は必ずいる
- むしろ説明しやすくなる
「人生が制限される」
- 不安:できないことが増える
- 現実:
- 適切な支援でむしろ広がる
- 無理をしなくて済む
- 自分らしく生きられる
「ショックで立ち直れない」
- 不安:受け入れられない
- 現実:
- 最初はショックで当然
- 時間と共に受容できる
- サポートグループもある
心理的サポート
- カウンセリング併用
- 当事者会参加
- 家族の理解
- 段階的な受容
社会的な影響
情報開示の選択
開示する必要がない場面:
- 友人関係全般
- 趣味のコミュニティ
- SNS
- 日常生活
開示を検討する場面:
職場での開示:
- メリット:配慮を受けられる
- デメリット:偏見の可能性
- 判断基準:職場の理解度
パートナーへの開示:
- タイミング:信頼関係ができてから
- 伝え方:困りごとベースで
- 反応:理解してくれる人を選ぶ
保険への影響
生命保険:
- 既契約:影響なし
- 新規:告知義務あり
- 対策:診断前に加入検討
医療保険:
- 注意:加入制限の可能性
- 代替:共済や団体保険
【実践】診断を受けるまでの流れ
1. 事前準備
セルフチェック
オンラインテスト:
- ASRS(ADHD向け)
- AQ(ASD向け)
- RAADS-R(ASD向け)
※あくまで目安、医師への説明材料として活用
困りごとリストの作成
仕事での困りごと:
- 締切を守れない頻度
- ミスの種類と頻度
- 人間関係のトラブル
日常生活での困りごと:
- 忘れ物の頻度
- 片付けられない程度
- 睡眠の問題
過去の困りごと:
- 子供時代の特徴
- 学生時代の困難
- 職歴と退職理由
情報収集
必要なもの(あれば):
- 母子手帳
- 通知表
- 職場の評価(参考)
2. 病院選びと予約
病院の選び方
専門性:
- 発達障害専門外来
- 精神科・心療内科
- 大学病院
確認事項:
- 成人の発達障害対応可
- 心理検査の実施
- 待機期間
- 費用の目安
予約時の注意
- 初診は2-3ヶ月待ちも
- キャンセル待ち活用
- 複数候補を検討
費用の目安(保険適用の場合)
- 初診:3,000-5,000円
- 心理検査:10,000-20,000円
- 診断書:3,000-5,000円
3. 診察と検査
初診
- 時間:1-2時間
- 内容:
- 主訴の聞き取り
- 生育歴の確認
- 現在の困りごと
- 既往歴・家族歴
- 持参物:
- 困りごとメモ
- 母子手帳等
- お薬手帳
心理検査
知能検査(WAIS-IV):
- 知的能力の評価
- 所要時間:2-3時間
- 内容:言語・動作性IQ
発達特性検査:
- CAARS:ADHD症状評価
- AQ/ADOS:ASD特性評価
- その他:病院により異なる
診断
総合判定の要素:
- 検査結果
- 生育歴
- 現在の困難
- 日常生活への影響
結果:
- 確定診断:ADHD/ASD等
- 傾向あり:グレーゾーン
- 該当なし:他の要因検討
【診断後】次のステップ
診断を受けた場合の選択肢
治療の選択
薬物療法:
- 開始:少量から徐々に
- 調整:効果と副作用のバランス
- 継続:定期的な通院
心理療法:
- 認知行動療法
- SST(社会技能訓練)
- マインドフルネス
- 頻度:週1〜月1回
※薬物+心理療法の併用が効果的
生活の工夫
すぐにできること:
- スケジュール管理アプリ導入
- タスクの見える化
- ルーティン作り
長期的な取り組み:
- 職場環境の調整
- 支援者ネットワーク構築
- ライフスタイル見直し
情報開示の段階的アプローチ
- Level1:信頼できる人にだけ
- Level2:必要に応じて職場に
- Level3:オープンにする(任意)
グレーゾーン・診断がつかなかった場合
グレーゾーンの理解
- 特性はあるが基準未満
- 困りごとは本物
- 支援は必要
活用できるもの
医療:
- カウンセリング
- 一部の薬(医師判断)
- 定期的な相談
自助:
- 当事者会参加OK
- 書籍・情報活用
- 工夫の実践
仕事:
- 上司への相談
- 産業医面談
- 自主的な配慮依頼
他の可能性
- 適応障害
- 不安障害
- うつ病
- HSP(繊細さん)
→別アプローチで改善可能
【体験談】診断を受けた人・受けなかった人
「診断を受けて人生が変わった」(ADHD・32歳)
診断前
仕事:
- 転職5回
- 評価は最低ランク
- 自信喪失
生活:
- 部屋はゴミ屋敷
- 借金100万円
- 人間関係崩壊
診断後の変化
治療:
- コンサータ服用開始
- 週1カウンセリング
- 生活習慣見直し
3ヶ月後:
- 仕事のミス激減
- 部屋を片付けられた
- 初めて貯金
1年後:
- 昇進した
- 借金完済
- 彼女ができた
メッセージ
「診断は終わりじゃない、始まり。適切な治療とサポートで、こんなに変われるなんて思わなかった。もっと早く受ければよかった。」
「診断は受けずに工夫で対応」(ASD傾向・35歳)
経緯
- セルフチェック高得点
- 明らかにASD傾向
- でも診断は受けない選択
理由
- 現状で何とかなっている
- レッテルを貼られたくない
- 保険の問題
対策
- ASD関連書籍で勉強
- 当事者会には参加
- 職場には傾向として説明
- 独自の工夫を実践
現在
- エンジニアとして活躍
- 理解ある職場
- 結婚して子供も
- 診断なしでも幸せ
考え
「診断は一つの選択肢。必須じゃない。大事なのは自己理解と工夫。自分に合った選択をすればいい。」
【判断基準】診断を受けるべきかチェックリスト
診断を検討すべき場合
困りごとの程度 □ 仕事で重大なミスを繰り返す □ 人間関係で深刻なトラブル □ 日常生活に支障 □ 二次障害(うつ・不安)
必要性 □ 薬物療法を試したい □ 職場に配慮を求めたい □ 自己理解を深めたい □ 支援を受けたい
様子を見てもいい場合
□ 工夫で何とかなっている □ 困りごとが限定的 □ サポートは十分 □ 診断のデメリットが心配
どちらでも
ポイント:正解はない
大切なこと:
- 自分の幸せ
- 生きやすさ
- 納得できる選択
まとめ:診断は手段、目的は生きやすさ
燃え尽き症候群を防ぐ方法については発達障害エンジニアの燃え尽き症候群を防ぐ持続可能な働き方も参考にしてください。
発達障害の診断は、あなたの人生をより良くするための一つの手段に過ぎません。診断を受けても受けなくても、大切なのは自分らしく生きること。
この記事のポイント
- 診断にはメリット・デメリット両方ある
- エンジニアとしてのキャリアにプラスになることも
- 診断を受けない選択も尊重される
- 最終的には自分の判断が大切
診断を検討している方へ
- まず信頼できる人に相談
- 情報収集を十分に
- 焦らず自分のペースで
- どんな選択も間違いじゃない
最後に
診断は、あなたを定義するものではありません。あなたの困りごとを理解し、より良い人生を送るためのツールです。
診断を受けるにせよ受けないにせよ、あなたの価値は変わりません。エンジニアとしての能力も、人としての魅力も。
自分にとって最善の選択をしてください。そして、どんな選択をしても、あなたを応援しています。
診断後の転職・キャリアを考える方へ
診断を受けた後、自分に合った環境で働くことを考えている方は以下のサービスが役立ちます。
ITエンジニア専門
- レバテックダイレクト:登録しておくと企業から直接スカウトが届く
- レバテックキャリア:IT専門の転職エージェント
障害者雇用での転職
就労移行支援
- atGPジョブトレ 発達障害コース:発達障害に特化した就労支援
この記事を書いた人
診断を経て働き方を見つけたADHDエンジニア。30歳でADHDの診断を受け、その後コンサータとカウンセリングを併用。自分の特性を理解してからは、フルリモートで集中しやすい環境を選び、生産性が大幅に向上。「診断は終わりではなく始まり」という経験を伝えるために発信中。
この記事は、診断を受けた/受けなかった発達障害傾向のあるエンジニア30名の経験を基に作成しました。医療的なアドバイスではありません。
ご注意
この記事は個人の体験に基づくものであり、医療的なアドバイスではありません。 発達障害の診断や治療については、必ず専門医にご相談ください。 また、記載されている情報は執筆時点のものであり、最新の情報と異なる場合があります。
関連記事

発達障害エンジニアのインポスター症候群克服法|自分の価値を正しく認識する方法
技術力はあるのに自信が持てない発達障害エンジニアのために、インポスター症候群の原因から実践的な克服方法まで徹底解説。実績ログ、認知の歪み修正、特性の強み変換など、今日から始められる具体的テクニックを紹介します。

発達障害者のための睡眠改善ガイド|質の高い眠りで仕事のパフォーマンスを上げる方法
発達障害者向けの睡眠改善完全ガイド。ADHD・ASDの睡眠障害の原因と対策、寝る前のルーティン、睡眠環境の最適化、生活習慣の改善など、80人以上の実践法と睡眠医学の知見から解説。仕事のパフォーマンスを上げる睡眠習慣を紹介。
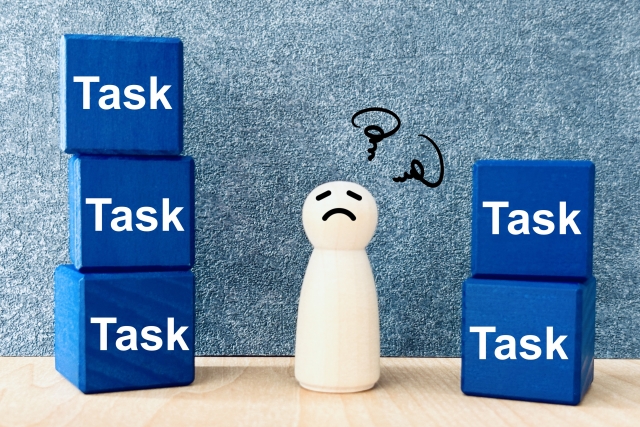
発達障害エンジニアのタスク管理術|先延ばしを防ぐ10の方法
発達障害者が先延ばしをしてしまう脳科学的理由と、特性に合わせた10個の具体的なタスク管理手法を紹介。ADHD・ASDエンジニアの実践例から学ぶ、継続できる仕組みづくりを解説します。